トップ › 脳疾患・骨折・関節手術の後には / 脳疾患(脳障害)のリハビリテーション
脳疾患(脳障害)のリハビリテーション
1廃用症候群※予防

※廃用症候群とは、ベッド上で動かず寝たきり状態となることで、筋肉が萎縮し衰え関節が硬くなり運動機能が衰えた状態のことをさします。ほかにも、身体の様々な器官が機能しにくくなり、寝たきりによる床ずれ、深部の静脈での血液のかたまり形成(深部静脈血栓症)、感染症などさまざまな合併症が起こります。
2日常生活動作の自立
急性期を脱し病態や血圧が安定してきた頃、症状に応じて様々なリハビリテーションが開始されます。基本的には、日常生活を行う上で必要な動作が行えるよう運動機能・嚥下機能・高次脳機能などを改善させるリハビリテーションが中心となります。
| 後遺症の名称 | 主な症状 | |
|---|---|---|
| 運動障害 | 運動障害 | 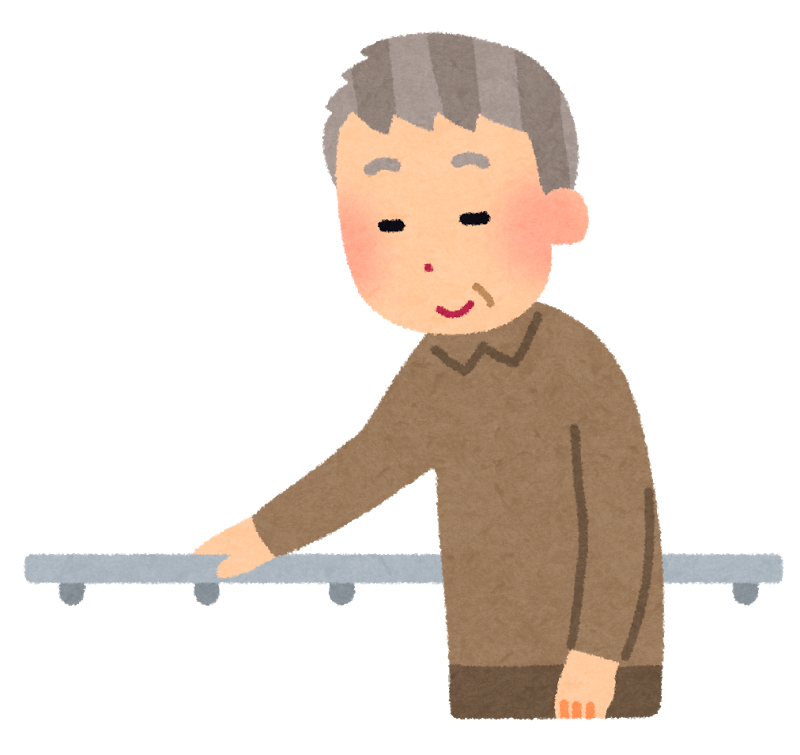 |
| 嚥下障害 | 嚥下障害 | 言語聴覚士による機能の評価、内視鏡やX線透視装置を用いた飲み込みの評価を行います。発声や舌の運動、首回りや肩の筋肉を動かしたり、舌や喉の奥を刺激したりする間接的訓練、その人の機能に応じた食事形態で飲み込みの練習をする直接嚥下訓練などをしていきます。急性期で口や鼻から管を入れて流動食を流して栄養管理(経管栄養)をしていた方も、これらの訓練を行うことで多くの方は口から食べることができるようになります。 |
| 言語障害 | 言語障害 | 言語聴覚士による機能評価を行い、機能に応じ発声練習・理解の向上、ゆっくり話す練習や舌の運動、口周りのストレッチや状況に応じて文字盤や日常よく使う言葉をカードを用いたコミュニケーションの練習などを行います。 |
| 高次脳機能障害 | 高次脳機能障害 | 言語障害以外の障害として、注意障害や遂行機能障害、半側空間無視、失行、失認などさまざまな機能評価を行い、先ず障害を認識して頂くことから始めます。次にその人の障害に応じて、日常生活動作を確実に危険なく行えるにはどのような点に注意すべきか理解を深め、繰り返し同じ行動を練習する、メモなどを用いて記憶の曖昧さを補うなどの工夫をしていきます。 |
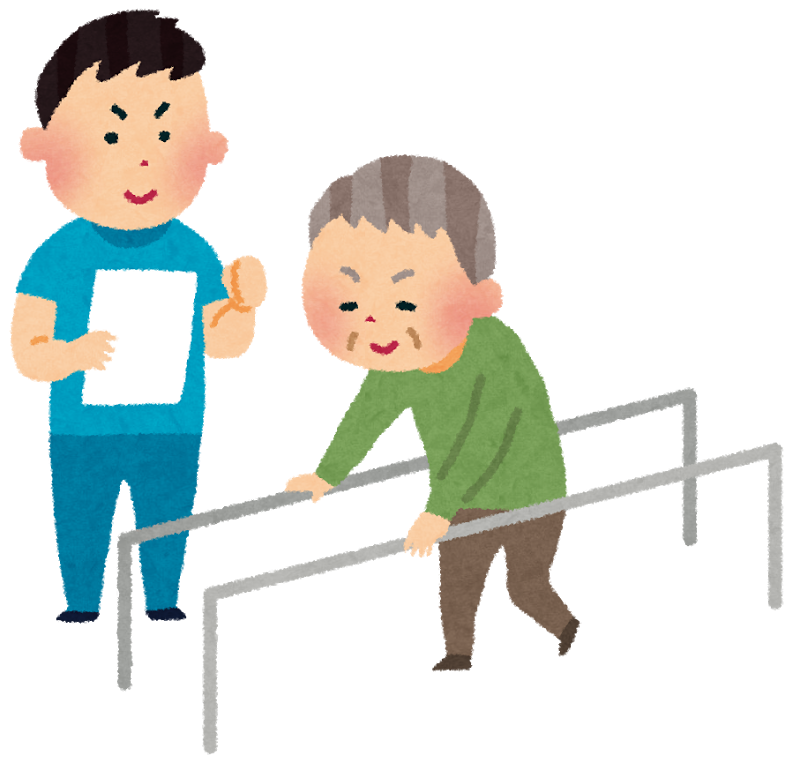
一度回復した機能も、退院後何もしないでじっとしていると再び機能低下が進みますので、退院後も外来や介護保険を利用したリハビリテーションを続けることはきわめて重要であると言われています。



